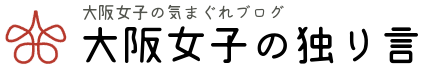大阪といえば粉もん文化
大阪のソウルフードといえば粉もんです。
粉もんというのは名前の通り、小麦粉を使って作っているメニューのことを指します。
お好み焼きやたこ焼きが最もメジャーであり、大阪の人は頻繁に自宅で作っていますし、粉もんをおかずにご飯を食べるとも言われています。
この粉もん以外にも大阪のソウルフードといえるものがあり、それがイカ焼きです。
イカ焼きは全国的に食べられるものですが、色々な種類があるのが特徴です。
大阪のイカ焼き
イカ焼きというと、縁日やバーベキュー、居酒屋で登場するメニューを想像する人が多いものです。
スルメイカのようなイカから内臓を抜き取り、胴体と足の部分を丸焼きにして食べるものを多くの人は想像します。
タレをつけて焼いた姿焼きのようなものや、ホイル焼きにして内臓も一緒に焼いたものなど、種類はいくつかあります。
しかし、大阪で言われるイカ焼きは粉もんの延長線上にあるものです。
作り方としては小麦粉をメインとした生地の中に細切れのイカを入れ、平たく焼いて二つ折りにして食べるものがポピュラーです。
大阪でイカ焼きを食べるときには注意を
大阪でイカ焼きと注文すると粉もんスタイルの大阪風のイカ焼きが登場します。
そのため、一般的な多くの人が想像するイカ焼きを食べたいと思ったらイカの姿焼きと注文することが必要です。
実際、大阪では屋台でもイカ焼きとイカの姿焼きと二つのお店が出店していますし、居酒屋でもメニューとしてイカ焼きとイカの姿焼きとがあります。
別々の食べ物として存在していますから、自分が食べたいのがどっちかを考えて注文しなければならないのです。
大阪のイカ焼き文化の始まり
大阪で他の地域とは違った形のイカ焼きがメジャーとなったのはいつからでしょう。
実はルーツはとても古く明治末期にはイカ焼きの原型となるものが誕生したと言われています。
当時はメニューとして販売されていたのではなく、せんべい屋の職人たちの賄いメニューとして食べられていたとされています。
しかし、それ以外にも色々と説があり、実際にはどのような始まりであるかは不明です。
他の説には、住吉大社の境内で屋台に出店していたのが最初という説もありますし、韓国のチヂミからヒントを得て大阪流にアレンジしてイカ焼きができたという説もあります。
このような色々な説はあるものの、大阪のイカ焼きを完成させたのは昭和25年創業の桃谷いかやき屋桃谷本店であると言われています。
創業者は上下両面を一度に焼き上げる専用の機械を発案してイカ焼きを作り販売していたとされています。
ここから色々なお店へと広まっていき、たこ焼きに並ぶ縁日の定番メニューとして大阪の粉もんグルメの一つになったのです。