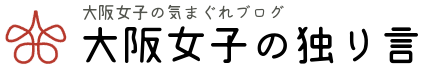歴史と文化が融合する大阪城
大阪平野の中央に位置し、大阪城公園として整備されています。
大阪城は、日本の歴史における重要な象徴的建築物で、その歴史的背景は興味深いものです。
大阪城の建設は、豊臣秀吉によって1583年に始まりました。秀吉は戦国時代の末期から安土桃山時代にかけての武将で、日本を統一し、天下人(覇者)となりました。
秀吉は自身の権威と統治を象徴するために、大阪に豪華な城を築きます。
秀吉の死後、大坂の陣(大坂夏の陣と大坂冬の陣)で落城。
徳川家康の指示のもと、二代目将軍である徳川秀忠が築城主となって現代に残る大坂城が築かれました。
明治時代になると、廃城令により多くの城郭が取り壊されましたが、大坂城は保存されました。
現在は博物館として公開されており、豊臣秀吉や徳川家康の像や甲冑、刀剣などが展示されています。
大阪城は、歴史と文化が融合する観光地です。
大阪城の天守閣
大阪城の天守閣は全部で8つのフロアに分かれています。
展示・展望台エリア
天守閣の1階から7階まで、大阪城や豊臣秀吉の資料が展示される博物館になっています。
大阪城の復元模型や甲冑、刀、当時の様子を再現したミニチュアが展示されています。
時期によって展示物が変わるため、詳細については公式HPからご確認ください。
8階は大阪の街を一望できる展望台になっています。
日没後はライトアップ
天守閣は毎日日没から24時までライトアップされています。白く輝く天守閣が見られます。
門や櫓も間接照明により、ミステリアスな雰囲気です。
美しい庭園と壮大な建造物
天守閣の内部には、大阪城の歴史や秀吉の生涯を紹介する展示物があります。また、最上階からは大阪市内の景色を一望できます。
大阪城公園と庭園は、四季折々の自然美を楽しめる場所です。
春には約3000本の桜が咲き誇り、夏には緑豊かな木々が涼しげに見えます。秋には紅葉が美しく色づき、冬には雪景色が幻想的です。
公園内には、茶室や梅林などの史跡もあります。また、年間を通してさまざまなイベントが開催されており、花火大会やライトアップなどが楽しめます。
大阪城観光の魅力は、美しい庭園と壮大な建造物の両方を堪能できます。
歴史や自然に興味がある方にはぴったりのスポットです。
桜門
桜門は、大阪城の本丸(中心部)への正門です。
名前の由来は当時、このあたりに桜並木があったためだそう。その桜門は明治維新によって焼失してしまいました。
現在の桜門は明治20年に再建されたもので、国の重要文化財に指定され、多くの観光客が足を止めています。
千貫櫓(せんがんやぐら)
千貫櫓は大手口を北西から横矢で防御する位置にある櫓です。大阪城内で最も古い建造物のひとつで重要文化財に指定されています。
現在の櫓は江戸時代に再建されたものです。
元々は石山合戦の際に横矢が効果的に飛んでくる階櫓に苦戦させられ、織田信長が「あの櫓を落としたものは千貫文の銭を与えても惜しくない」という逸話からつけられたそうです。
普段は外からの見学になりますが、年に1、2回内部が公開されています。
真田幸村の抜け穴
大坂冬の陣で真田幸村(信繁)が、当時真田丸があったとされる現在の三光寺に大阪城へつながる地下道を作ったとされたものです。
この地下道を使い、豊臣方の諸将と連絡していたといわれていますが、実際に利用していたという史料はないとのこと。
どうしてこのような伝説が残ったのかというと、当時の人々が幸村のような武将なら、地下道を掘る奇策を用いたと考えたとされています。
現在は残念ながら鉄格子がされ中に入れません。
大阪城豊國神社
大阪城の二の丸跡に位置し、豊臣秀吉、豊臣秀頼、豊臣秀長を主祭神とする神社であり、豊臣家の栄華と歴史に深く関連しています。特に、豊臣秀吉を祀ることで知られています。
明治天皇の勅命より明治12年(1819年)に京都の豊國神社の別所として、中之島字山崎の鼻(現在の中央公会堂)に建てられました。
その後、昭和36年(1961年)に現在の場所へ。
境内には1972年に作られた秀石庭があります。
大阪城を回る時間
大阪城を回る所要時間ですが、天守閣以外の城内の二の丸や本丸、西の丸と呼ばれる区画は広いため、ゆっくり回ると1時間半はかかるでしょう。
メインの天守閣は展示物や体験コーナーがあり、見て回るだけでも30分は必要です。
大阪城へのアクセス
大阪城へのアクセスは、電車、バス、車のいずれでも可能です。
電車の場合は、JR大阪環状線の大阪城公園駅か、地下鉄中央線の森ノ宮駅が最寄りです。
バスの場合は、大阪シティバスの大阪城大手前か馬場町が便利です。
車の場合は、大阪城公園内に有料駐車場がありますが、台数に限りがあるので早めに行くことをおすすめします。
大阪城の営業時間は、9時から17時までです。12月28日から1月1日までは休館日となります。
入場料金は一般600円、中学生以下無料です。また、20人以上の団体や障害者手帳を持っている方は割引料金が適用されます。詳しくは公式サイトをご覧ください。
大阪城周辺のおすすめ観光スポット
大阪城周辺の観光スポットには、歴史や文化に興味がある人にぴったりの場所がたくさんあります。
大阪城公園は、四季折々の美しい自然を楽しめる広大な敷地で、桜や紅葉の名所としても有名です。公園内には、大阪城ホールや大阪城西の丸庭園などの施設もあります。
さらに、大阪城周辺には、大阪博物館や大阪国際平和センターなどの文化施設も多くあります。
これらの施設では、大阪の歴史や文化について学ぶことができます。大阪城周辺は、大阪の魅力を感じることができる観光スポットです。
造幣博物館
明治44年(1911年)に火力発電所として建てられた建物で、造幣局構内に残る唯一のレンガ造りの西洋風建物です。
昭和44年(1969年)に造幣博物館として開館しました。
2階では造幣局の歴史や金塊、銀塊に直接触れられるコーナーのほかに、東京・長野オリンピックで選手に授与された入賞メダルが展示されています。
3階では各国のさまざまな硬貨・貨幣が展示されています。
もりのみやキューズモールBASE
大阪市中央区にあるショッピングモールです。日本国内の商業施設では初めて屋上に本格的なランニングトラックを常設しています。
日本生命球場の跡地に建設されたことから施設名に野球の塁を意味するBASEを入れているそうです。
総合フィットネスクラブやカフェレストランなど49店が出店しています。
大阪企業家ミュージアム
大阪ゆかりの企業家105名の実績をパネルやゆかりの品、資料で一堂に紹介するミュージアムです。
企業家たちの高い志や勇気、英知を後世に伝え、次世代に切り拓く人づくり、ひいては活力ある社会づくりを目指すとしています。
ビデオコーナーもあり非常にわかりやすかったです。
北浜レトロビルヂング
明治45年(1972年)に証券会社の商館として建てられたレンガ造りの洋館です。一時期、廃ビルとなっていましたが、北浜レトロとして再生されました。
1階は洋菓子、洋食器、カフェグッズが販売されており、2階はおいしい紅茶がいただけるカフェになっています。
たくさんの人が並んでいました。かつての姿をそのまま残したまま今も建物を使っているというのは素晴らしいですね。
少彦名神社(すくなひこじんじゃ)
神農さんという愛称で親しまれている神社です。祀っているのは少彦名命と炎帝神農(えんていしんのう)。
少彦名命は大国主命(おおくにぬしのみこと)とともに日本を作ったといわれる神様で、医薬やまじない、温泉、酒蔵など幅広い力を持っています。
炎帝神農は古代中国の神様で、医療と農耕を伝えたといわれています。
少彦名神社がある道修町は薬の取引場所として発展した薬の街なのです。
当時の技術では薬の調合は難しいこともあったため、神頼みが普通でした。そのため少彦名神社は建立されたそうです。
ビルの谷間にあるこぢんまりとした神社ですが、結構趣のある神社でした。
大阪天満宮
菅原道真公を祀ることから「学問の神様」と呼ばれる大阪天満宮。毎年受験シーズンには多くの学生で賑わいます。
他にも厄除けや恋愛成就、商売繁盛などさまざまなご利益があります。
毎年7月24・25日に催される天神祭は日本三大祭の一つとして有名です。
お弁当を食べている人もいて、天満宮と言うより、「天神さん」と呼ばれ親しまれているのが伝わって来ました。
大阪水上バス アクアライナー
大阪市内を流れる大川を周遊する観光船です。船内アナウンスつきで大正レトロビルの中央公会堂や造幣局、大阪城などを望むことができます。
途中、天神橋や天満橋、銀橋など大川に架設された橋も見どころです。
夜にはライトアップされた街並みや幻想的な水面など、ロマンティックな夜を堪能できます。
船内には売店やお手洗いも完備しています。
暑い中でしたが船内は冷房が効いており、気持ちいい船旅となりました。行ったことのある場所も船からの視線はまた違っていて不思議な感じです。
今度は桜の季節に乗ってみたいです。
道頓堀
みなさんご存じ大阪市中央区の繁華街の町名です。江戸幕府が大阪を直轄領として開拓し、芝居町として発展したのがはじまりと言われています。
現代もたくさんの観光客で賑わっています。大阪に来たらココが1番大阪を感じるのではないでしょうか。
食い倒れ文化でも知られる道頓堀は食べ物がおいしいことでも有名です。周りには有名なたこ焼き屋さんや飲食店が並ぶ有名なスポットです。
北に飲食店が集中し、南側には娯楽施設が多くあります。
定番スポットのグリコの看板や観覧車付きのどデカいドンキホーテ、くいだおれ人形に、カニ道楽など。
まさに道頓堀は大阪を代表するスポットですね。かなりの人混みなので人酔いしそうでした。